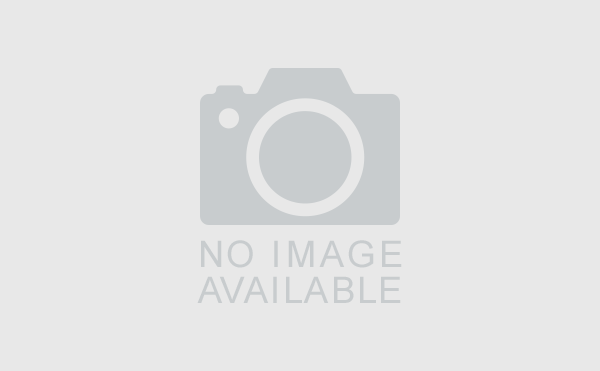白いマフラーをなびかせ散っていった若者たち
2012年07月03日
子供の頃、父は戦争の話をよくしてくれた。ジャワ島やインドネシアでの自転車部隊だったこと、地元民を捕まえて顔の布に水をかける拷問を見たこと、突撃のとき隣の兵に弾があたり死んだこと、上空で始まった日本機と敵機の空中戦では日本機の方が落とされてと思い出して悔しそうに話します。日本に帰っても仕事がないだろうからと、現地に残った男が何人かいたとも言っていました。興味津々で聞いていたのだけどひとつどうしても聞きたいことがあった。
「父ちゃんそのとき人を殺したの」
「・・・・・」 戦争とはいえそれは大問題でした。
返事は覚えていない。多分無かったのではないか。「ああ殺したよ」と言われれば絶対に記憶に残っているはずだから。あっても父はあえてそれを言わなかったのか。
台湾に帰ってきて台北の軍司令部にいたのが後藤田正晴でした。彼は東京帝大を出て官僚から軍隊に入った後、台湾の陸軍主計少尉になっていたようです。酒を飲んで叱られたこと、戦争が終わって翌年引き揚げるときにあいさつに行ったら風邪だかで寝込んでいたことなど話してくれました。
思うに父は大正6年の生まれ、日中戦争の頃に兵役についたので助かったのではないか。その後に生まれた男たちは泥沼の激しくなった戦闘でみんな死んでいった。
母も台湾の生まれで優雅な生活であったようです。小学校にはハイソックスにランドセルで通学していた。80年以上前です。東京の麹町や青山は別にしてまだ着物に下駄やぞうりの時代だったはずです。子供の頃から牛乳を飲み、ロシア人がパンを売りに来たという。上海や台北がいかに東京をまねたハイカラな街だったかが窺い知れます。それが戦後引き揚げて自分たち子供3人がバナナ1本を三つに分けて食べるような貧乏生活になり、高度経済成長の日本ではめずらしい親より子供が貧しいという姿に母も悲しかったのではないか。
台湾ではあまり爆撃はなかったがそれでも人が泥人形のようになって死んでいたり、飛行場から若者が白いマフラーをなびかせ特攻に向かうのを手を振って見送ったことなど話してくれます。よく記録映画でその光景を見ることは今でもできますがひとつ当事者でないと云えないことで特攻機が出撃する日時は事前に知らされていなかった。これは母から聞いた以外は今まで聞いたことがありません。急に召集がかかって飛行場に向かっていたようです。
「白いマフラーがなびいてね、あんなに若い男たちが死んでいったのね」
台湾は今でも親日の国ですが、日本人が引き揚げるとき駅舎や港でそれまで下で働いていた台湾の人が一緒に連れて行ってくれと泣いてすがっているのを何度も見たそうです。
官房長官、副総理をつとめたカミソリ後藤田は7年前91才で亡くなりました。対比するかのように生きた父は今年1月、94才、もう少しで95才というところで生涯をとじました。
母はつぶやく。「あの戦争さえなければ」
毎年夏になると終戦特集で新聞などに思い出が綴られます。兵隊さんより当時子供だった人々の話が多くなりました。
この平成の世に紛れ込んだ昭和のイメージを私は迷い児のように追うだけです。
米田正之