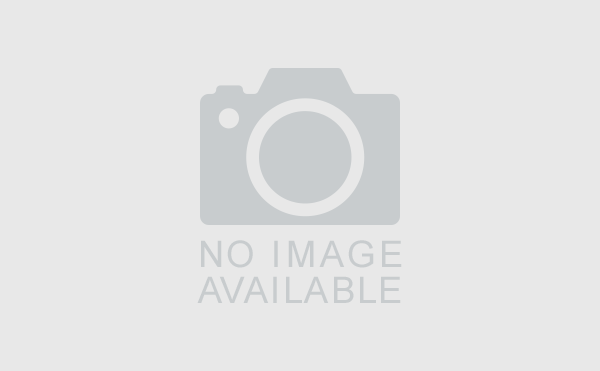ラテンが流れていたころ
2017年04月30日
うすぐもりの昼下がり物憂いメロディーがどこかの家のラジオから流れてくる。ラテンの曲は今思えば「セレソ・ローサ」や「南京豆売り」だったか。地方都市のメインの商店街であるアーケード街の宣伝でけだるいラテンに合わせてそれぞれのお店の紹介が短く続けられていく。
このあたり一帯は戦後の繊維産業を支えた機織工場が多くあり近所の主婦を4,5人雇っているところから家族だけのところまで何十という工場が常にガチャガチャいう音を響かせていた。夜12時頃に音が止んだと思ったら明け方5時にはもう聞こえ出すというとにかく働く土地柄であった。今やたら祭日が多くなってこれは公務員が決めたものだが彼らはいくら休んでも給料は変わらないが零細企業では給料は変わらなくても売り上げが下がることを知っているのだろうか。これが発言力の弱みというところか。
その頃ラジオから聞こえていて覚えているのは春日八郎の「赤いランプの終列車」や「お富さん」で調子のいい曲調と歌のうまさが子供心にもすごいなと感じたのだろう。
戦後の一時期とは違うがまだ混乱の余韻というのが残っていたのか押し売りというのがよくあった。漫画で描かれている出刃包丁を床に差してゴムひもを売るとかのそれで家に男がいないとかなり脅しが前面に出ていた。ある日隣の家に来ているのを見た母は部屋の奥に隠れて少年の自分が矢面に立たされることに。「お母さんいる」と聞かれておもわず部屋に向かうが母は無言で顔の前で手を必死に振って居ない事をアピールしている。ここでまだ5才の男子の一世一代の演技で周りをキョロキョロしながら「どっかにいって母ちゃんいない」と答える。百戦錬磨の行商人がそれを見抜けないことはないのだが、その中年の男はニッコリ笑って何か言った。それは覚えていないのだがたぶん「しっかり遊んでるか」とかいうことだったろう。隣の家に向かう後姿を安堵感いっぱいで眺めた。
工場から聞こえる音、ラジオから流れるラテンや流行歌、心象風景の音は戻すことの出来ない長い時間や戻ることのないだろう現実の中で想い出せばいつでもすぐに聞こえてくるのだ。
米田正之