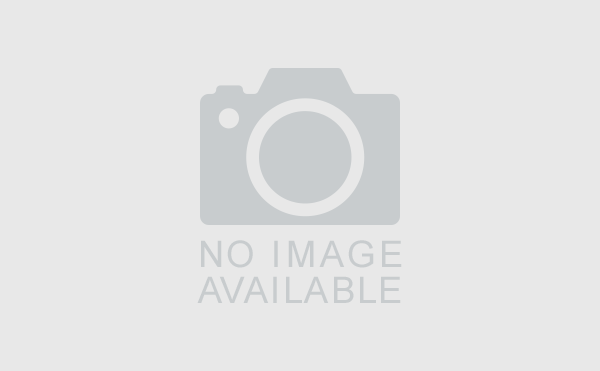的外れな自己責任論
2019年07月13日
東京の例えば日本女子大の前身の専門学校で良家の子女がお勉強をしている頃、遠く飛騨から岡谷の製糸工場に来た同じ年代の娘たちは悪臭漂う劣悪な環境の中長時間働いていた。
かつてほんの一握りの裕福な層は今はプチ富裕層その周辺まで含めれば国民の2割ぐらいになる。対して私が入っている貧困層も同じほどいる。汲々とした生活でゆとりのない年金生活者が大勢いる。富裕層の人たちには年金支給停止、相続税も含め課税の強化、年金局長をはじめとする官僚が退職金や天下りで何億ものお金を巻き上げていく制度の廃止。官僚は退職したらハローワークで職を探しましょう。仕事は沢山あります。新たな天下り先を作るのはやめましょう。法人税を上げアメリカへ渡す余計な防衛費を減らして浮いたお金を年金に回しましょう。日本の公的年金は賦課方式なのだからもらわなくても老後は生きていける人たちに支給している方が問題だろう。消費税も上げなくていい。今はやりのMMT 現代貨幣理論で消費税を廃止できるか議論すべきで貧困層がより重い税負担を強いられる政策は変えなければならない。
長く激しいイデオロギー対立の時代が終わり世界中で貧困と格差の是正が問われているがこれはもともと対立の根源にあったものだ。イギリスはアフリカから奴隷をアメリカに送り莫大な利益を得産業革命を成し遂げそれが工場で働く困窮者を生み出しそれを見たマルクスは思想を発展させていく。貧困格差対策が政治の基本である。日本では族議員、官僚、利益集団による利益誘導型の政治となっている。発言力が強い方に政策も沿っていく。若者は皆忖度名人になってしまっていいようにやられている。格差があることが当たり前になって考えることさえしない。堀木訴訟や朝日訴訟などで権利意識を導いて頂いた先人方の努力はどこに行ってしまったのか。
お金持ちや成功した人が寄付をする習慣がないのは何も税制の問題でなく国民性なのだから直ぐに自己責任と言い出す。自分は頭がよかったからとか死ぬほど頑張った、努力したからと言ってもそれも含め全て周りの力によるものでそれがないとスタート位置にも立てない。その言葉はいかにも的外れと言えよう。明治の中頃でも貧窮者に手を貸すのは怠け者を助長させるだけという考えが時の為政者だけでなく一般に多くあった。全く変わっていないのだ。これでは明治時代に逆戻りではないか。強いものが好きならライオンやトラが一番の世界に行ってください。
貧困格差が拡大すると社会不安、社会的緊張、政情不安が生まれることを世界の歴史が教えているが自分たちの意見を主張するのが市民の権利であるとは広く認められていても日本ではそうでないように世界の常識が通用しないことがいくらでもあってこのまま何も変わらないで何百年と続くという予測も有りなのである。新しい階級闘争が始まろうとしているのではないか。分断された階級の社会をまとめ上げる新しいシステムを、資本主義、中国のように経済を優先させた一党独裁、これに代わる新しい経済システムを必要としている。これは決してあり得ないことでもなく必要とするところには必ず生まれるものできっと将来出来ている。
日本の発展の礎となった名も無き若い娘たちの中で後年ノンフィクション作品やその映画化により一人の名前を知ることになる。政井みねが「あー飛騨が見える」と言って野麦峠の一輪の花となって110年遥々東南アジアから来られた若者が過酷な労働と低賃金にさらされているという。今この時代に信じられないが東南アジアは決して貧しい国々ではない。明日死ぬかもしれない私のような年寄りが多い日本と違い若い人が多く急成長を遂げている。いつか日本を追い越していくだろう。人権よりも上下関係や協調できるかが優先される、入管で殺されるそういう国に来たいだろうか。言うまでもなく貴重な人たちなのだから大事にされるべきだろう。その時々の社会の中で困窮しながらも働く人々こそがその社会を映していて、どう生きていたかを知ることでどういう時代であったかが初めて理解出来る。それは昔も今も変わらない。
深い緑の木々の中を縫うように続く道に木漏れ日が注ぐ野麦峠も厳冬では猛吹雪となる。どこまでも青く輝く空も白だけの世界で何も見えない。少女たちが歩いた道は過酷であり人生そのものであった。
米田正之