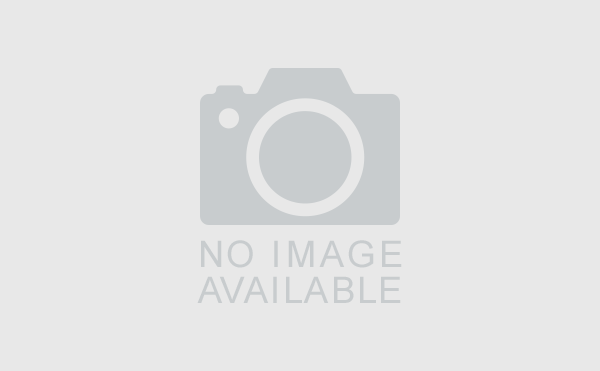慣習と宗教
2013年08月04日
日本より人口の少ないドイツでは800万人近くが生活保護を受けているのを伝えているか。保護を受けている人よりもっと厳しい人がいるというのも本来受けるべき人の7~8割は受けていないのだから当然だろう。国民と政治をつなぐのは利益集団と世論だけなのだからメディアがダメだと言ってもこれが日本の慣習、文化ではないだろうか。受けるべき人が受けないというのも日本人の価値観だから国民もメディアもこの呪縛から逃れられない。1000年後も変わっていないだろう。
パキスタンで女子が教育を受ける権利を訴え撃たれたマララさんを伝えるメディアは一斉に世俗派でないイスラムが悪いと言う。教育を受けたいという女子を殺そうというのは明白に間違いであるがそこにあるのは宗教というより慣習、因習ではなかったか。それほど昔でもない日本の日常会話で「女は嫁に行くんだから学校に行く必要が無い」とよく聞いた。実際自分の少し上の団塊の世代までは成績が上位なのに中学で終わっている女子が多くいた。純潔という言葉もあった。宗教というより長い間そこに暮らす人々の風習、習慣だろう。婚前交渉をした娘を親、親族が殺すのをよしとするのも女子の就学規制も人権を無視するようでいて意味があるものだったのだろう。ただ慣習や法は少しずつ変わっていく。イスラム教徒の多い国でも死刑を廃止しているぐらいだから。日本でもいつまでも弱者がだまってはいない。焼き討ちされて崩れ落ちる国会議事堂を見るだろう。300年後に。
西欧の価値観が正しいのですか。その代表のアメリカは商売の為、強い経済の為戦争を仕掛け直径何百メートルの範囲の人間を窒息させ丸焦げにする兵器を使って喜んでいる。国内ではお金がなければ医療も受けられない。キリスト教徒の多い政教分離のその国が偉いですか。まさに宗教とはなんなのか。ボブディランも歌っている「神が味方なら戦争を止めていただろう」。
明治の初め富岡製糸場に士族の娘たちが集められ女工哀史とは違った良好な労働環境ではあったが国の為、家の為と頑張りその後に出来た製糸工場で指導的な役割を担っていく。その和田英と同世代の亡くなった年も同じ津田梅子は一人でいいのであって200人も300人も必要ではなかった。学校なんてあまり関係ない、人が幸福でいられるか不幸かは教育を受けるか受けないかではないだろう。小学校を3年で中退して学校に行っていない自分が言うのだから本当だ。それをマララさんに話したいのだが遠いし、言葉が分らないし、なにしろ連絡先を知らない。
米田正之